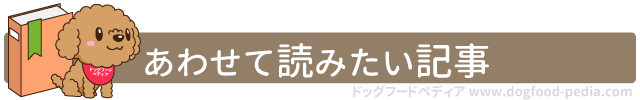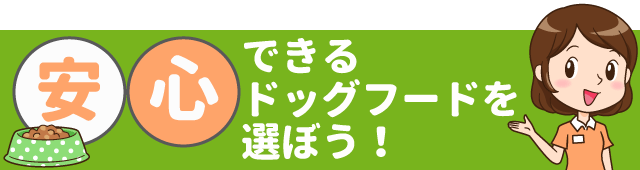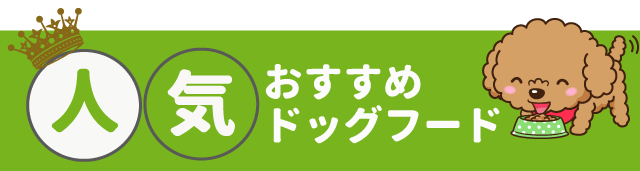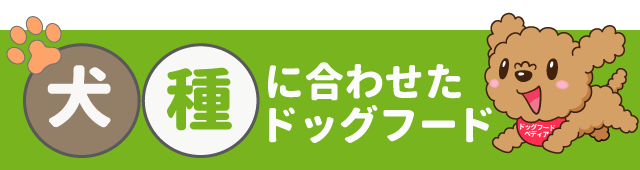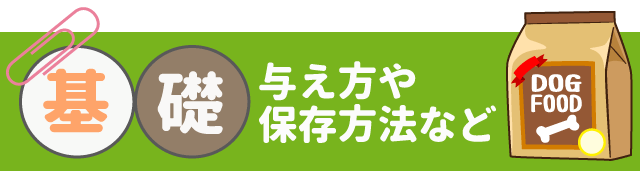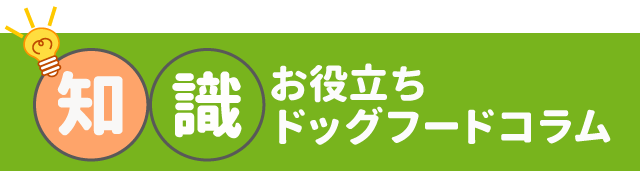ワンちゃんに必要な栄養とは? ~犬と人の身体の違い、必須栄養素の違い
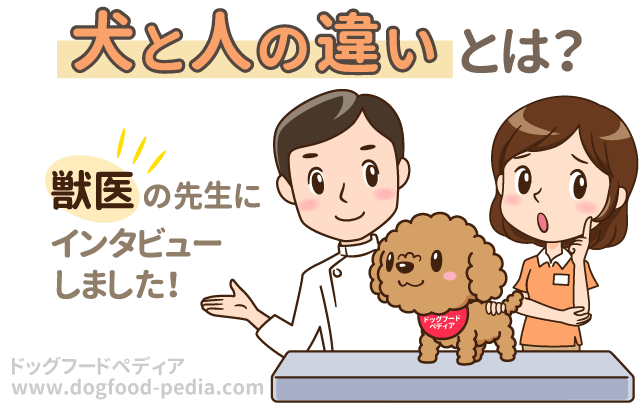
家族の一員であるワンちゃん。ドッグフードや犬用のおやつ以外にも、私たち飼い主が食べているものも欲しがります。
実際に与えると、野菜でも、くだものでも、チーズでも、おいしそうにペロッと食べるワンちゃんもいます。
しかし、おいしそうに食べるから何でもあげていいというわけではありません。
偏食になってしまうと栄養バランスが崩れますし、健康上の問題が出ることもあります。
犬と人間の栄養の違いを学んで、どのような点に気をつけてあげればいいのかを、考えていきましょう。
目次
| 犬 | 人間 | |
|---|---|---|
| 食性 | 肉食傾向の強い雑食 | 雑食 |
| 唾液中の消化酵素 | ない | ある |
| 小腸の長さ | 1.7~6m | 6~6.5m |
| 歯の数 | 42本 | 32本 |
| 大腸の長さ | 0.3~1m | 1.5m |
このように犬と人間に違いは様々です。
歯の数や、腸の長さなど一見すると、食には関係のなさそうに見えることも、食べているものの種類に大きく関係してくるのです。
【犬と人間の違い】食べものを得る方法の違い
肉食動物は肉を中心に食べ、草食動物は草を中心に食べます。雑食はこの中間です。
こういった単純に見える食の違いが、眼や耳の位置や、頭の形、歯の数、消化酵素の種類、腸の長さなどを決定づけているのです。
肉を食べるためには、獲物をしとめる必要があります。
肉食動物の代表例はライオンやトラですが、あの口を思いだしてください。立派な犬歯がありますね。犬歯は獲物をしとめるために重要な役割を持っており、犬にもあります。
一方、人間に犬歯の名残り程度しかなく、八重歯と呼ばれる歯が、退化した犬歯です。
人間は、咬みついて獲物をしとめることはなくなり、弓や槍を用いたり、狩猟のパートナーである犬に獲物をしとめさせていました。
また、食事の際も、生のままで食べるのではなく火を使い調理し、柔らかく食べやすく工夫するようになったことで鋭い犬歯は必要なくなっていったのです。
人間に一番近いと言われているサルたちは犬歯が残っています。
サルたちの一部は道具を使いますが、人間ほど道具を使うことに長けておらず、火を使って焼いたり煮たりはしません。
このような理由で人間の犬歯は退化し短くなったと言われています。
【犬と人間の違い】歯の違い
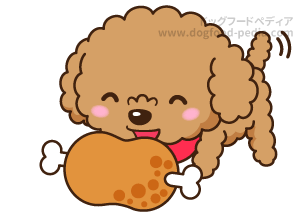 犬の奥歯が、どのような形をしているか知っていますか?
犬の奥歯が、どのような形をしているか知っていますか?
犬の歯は人間のように平らではなく、山のようにとがっています。
人間のもつ、平らな歯は、歯と歯の間に硬い繊維質のものなどをはさんで、すりつぶす役割を持っています。
犬のもつ山のようにとがった歯は、食べものをすりつぶすのではなく、細かく切り刻む役割を持っています。
歯の違いから、犬は本来肉食だということがわかります。
【犬と人間の違い】腸の違い
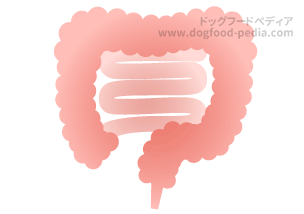 腸の長さを比較すると、犬より人間の方が、かなり長いことが分かります。
腸の長さを比較すると、犬より人間の方が、かなり長いことが分かります。
同じ人間でも農耕民族と狩猟民族とでは腸の長さが違い、農耕民族の方が長い腸を持っています。
腸の長さは野菜などの繊維分をどれほど摂取するかによって変わってくるのです。
消化しやすいものを多く食べる動物は腸が短く、消化しにくい繊維分を多く摂る動物の腸は長くなります。
腸の長さを比較すると、犬が肉食であることがわかります。
【犬と人間の違い】消化酵素の違い
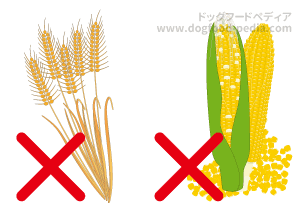 注目したいのは、口の中の消化酵素です。
注目したいのは、口の中の消化酵素です。
犬にはなくて人間にある消化酵素は、唾液アミラーゼと呼ばれます。
アミラーゼはデンプンを分解する消化酵素で、デンプンにアミラーゼが作用すると加水分解され、麦芽糖、ブドウ糖を経て小腸から吸収されます。
犬はこのアミラーゼを持っていないので、デンプンの分解は苦手ですが、α化デンプン(アルファ化デンプン)だけはアミラーゼを持たない犬でも消化することが可能です。
もし犬が、α化されていない穀物を多く含むドッグフードをたくさん食べ続けると、消化不良を起こしてしまいます。
このように、犬は唾液アミラーゼをもたないことから、穀類を含まないフード(グレインフリー)が誕生しました。
グレインフリーのドッグフードでは、炭水化物源としてサツマイモなどが使用されています。
【犬と人間の違い】必須栄養素の違い
ここまでお話ししてきた、犬と人間の体の違いをふまえると、犬が大切な家族の一員だからと言って、人間とまったく同じものを与えるのは不適切だということがわかってきます。
近年家族の一員である犬に手作り食を与える家庭が増えてきました。
手作り食や手作りおやつのレシピ本もたくさん出版されていますし、インターネットでも様々なレシピが紹介されていますね。
犬にとって必要な栄養をチェックしながら、手作り食とドッグフードについても考えていきましょう。
基本の5大栄養素
まず、簡単に栄養素のお話をしたいと思います。
栄養素は大きく分けて5種類あります。五大栄養素とは、炭水化物、タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルのことをいいます。これらを機能面から分類すると次のようになります。
- エネルギー源 : 炭水化物、タンパク質、脂肪
- 身体の構成成分: タンパク質、脂肪、ミネラル
- 生理機能 : タンパク質、ビタミン、ミネラル
このように様々な働きを担っているのが栄養素です。この五大栄養素の中から特にタンパク質とビタミン、ミネラルについて詳しくお話していきます。
必要な必須アミノ酸の種類が異なる
タンパク質が分解されるとアミノ酸に分解されます。食物として経口摂取しないと、体内で合成することができないアミノ酸のことを「必須アミノ酸」と呼び、これらは食物として取り込まなければ体内で不足してしまいます。
この必須アミノ酸は動物の種類によって異なります。
犬の場合必須アミノ酸は10種類です。犬と人間の必須アミノ酸を比較してみましょう。
| アミノ酸の種類 | 人間 | 犬 |
|---|---|---|
| グリシン | ||
| アルギニン | ||
| ヒスチジン | ||
| ロイシン | ||
| イソロイシン | ||
| バリン | ||
| リジン | ||
| メチオニン | ||
| フェニルアラニン | ||
| スレオニン | ||
| トリプトファン | ||
| タウリン |
例えば、犬はアルギニンを体内で合成できないため、必ずアルギニンを含む食品を経口摂取しなければなりません。アルギニンは豚ゼラチン、大豆たんぱく、鰹節などに多く含まれています。
アルギニンを全く含まない食事を与え続けていると、犬は高アンモニア血症を起こし、アンモニア中毒を起こして最悪の場合亡くなってしまいます。
犬に必要なビタミンとミネラル
 動物にとって重要なビタミンは13種類あります。
動物にとって重要なビタミンは13種類あります。
ビタミンA、D、E、K、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ニコチン酸、葉酸、ビオチン、コリンが重要なビタミンです。
この中でニコチン酸というビタミンが欠乏すると、犬では舌が黒くなる黒舌病という症状を示します。
微量元素ともいわれるミネラルも、体内のバランスを整えるために非常に重要な働きをしています。
犬は肉食動物なので、肉だけを与えればよいと誤解されることがありますが、ミネラルもしっかり摂らないといけません。
肉類はミネラルであるカルシウムが異常に少なく、リンが多い食品で、非常にバランスの悪い食べ物です。
カルシウムとリンのバランスは1:1~0.8が理想とされています。
ちなみに、牛のヒレ肉とかつおだと、以下のような比率になります。
牛のひれ肉(100g)= カルシウム 3mg、リン 180mg カルシウム:リン = 1:60
カツオ(100g)= カルシウム 8mg、リン 260mg カルシウム:リン = 1:33
このように、肉だけの食事を与え続けるとカルシウムの量が減少して骨の成長が阻害され、骨格の形成に異常が出てきてしまいます。
【犬とオオカミの違い】祖先オオカミから犬への進化
 犬の先祖と言われるオオカミです。
犬の先祖と言われるオオカミです。
では人間と生活を共にするようになった犬と、オオカミの違いはどこにあるのでしょうか?
オオカミとイヌのDNAを比較した結果から、興味深いことが分かりました。
世界各国のオオカミ12頭と、14犬種60頭の犬のDNAを調べたところ、36のゲノム領域に含まれる122の遺伝子に違いがみられました。
そのうちの19領域は、脳の発達や機能に密接に関係する遺伝子が含まれていました。
この脳の発達にかかわる部分が、犬が人間とともに生活できる柔軟性にかかわっている可能性が高いと考えられています。
また、デンプンと脂質の代謝にかかわる10の遺伝子にも違いがみられました。
その中の3つの遺伝子の突然変異が、犬のデンプン消化能力を高めていることが分かりました。
つまり、犬は長く人間と共生しているうちに、祖先のオオカミよりもデンプンの分解能力が高くなり、雑食寄りの肉食動物に進化してきたのです。
まとめ
犬に必要なカロリーの計算は、栄養成分表を見ながら計算していくと必要カロリーを満たすことはできますが、犬に必要なアミノ酸の確保や、ビタミンバランス・ミネラルバランスの計算を正しく行うことは、一般家庭では非常に困難です。
手作り食のほうが愛情がこもっているからと考えるかもしれませんが、ワンちゃんにとってはドッグフードが最もバランスの取れている食事と言えます。
何らかの理由で、手作り食を与える場合も、ドッグフードと手作り食を、うまく組み合わせることによって、犬に必要なビタミンやミネラルが欠乏しないように十分気をつけましょう。